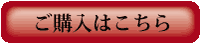恐怖のカレーのCMに登場する、"驚怖"の男。
一人深夜にカレーのパッケージを開ける、彼は一体何者なのか。
彼が目にしたのは恐怖か、驚怖か。
驚怖の男の噂に迫ります。
驚怖の男の噂
第参夜
暑さというのは、実に人を狂わせる。
外回りの営業から戻ってきたばかりのMは汗を拭うこともなくぐったりと椅子にうなだれた。古いパイプ椅子はMの全体重を預けるには頼りなく、ギシギシと耳障りな音を鳴らす。
その年の気温は異常であった。連日35度を超える猛暑が続き、日差しが鬼のように容赦なく照り続けていた。
不思議なもので、この暑さの中でも食欲が衰えることがないのだから困ったものだ。これだけ毎日汗をかいているのだから、一回りくらいサイズダウンしてもよさそうなものなのに。理不尽な体だ。などとぼんやりと考えながらMはため息をついた。
今夜は、無性にカレーが食べたい…。
そんなことをポツリと漏らすと、傍にいた同僚のOが自作のカレーを今夜ごちそうしようと声をかけてきた。
OはMの同僚にあたる男だ。心霊マニアでもあり、最近はもっぱらカレー作りに凝っているという。
物好きな男だと聞き流していたが、夜な夜な情熱を注ぐカレーがどんなものかというのはMにとっても気になるところではある。
しかしOは意味深な面持ちでこうも告げた。
ただし、今夜ごちそうするのはただのカレーではない。
恐怖のカレーなんだ。
恐怖のカレーだって?それはいったいどんなカレーなんだと尋ねたが、Oは食べてみてのお楽しみだとニヤリと笑うだけだった。
Mはますますこのカレーが気になってきた。ものは試しだ、ぜひごちそうしてくれ。
返事を聞いたOは、また、ニヤリと笑った。
その夜、Mの自宅のチャイムがなった。
時計の針は午後10時を指していた。
Oがきた。
そう思ったMはインターフォンを確認したが、そこにOの姿はなかった。
確かに、チャイムはなったはず…Mが玄関の扉を開けて確かめると、ポストに小さな箱が投函されていた。
ちょうどレトルトカレーの箱のようなサイズで、「恐怖のカレーを持ってきたから、一人で、食べるように」と書かれたメモがついていた。
Oの筆跡のようだ。いくら恐怖のカレーだからって、こんな演出までしようとは、少々タチが悪い。…だが、一段と面白くなってきた。最初は恐怖のカレーを訝しんでいたMも、すっかりこのカレーに興味をそそられていた。
さっそく部屋に戻ると、Mは一人、その箱をあけた。
…それは一瞬の出来事だった。
いや一瞬のようで、永遠のような…不思議な時間感覚の中、辺りは真っ暗で、叫び声に似た何か甲高い音が耳の奥に響く。出口のない迷路を彷徨うように無数の白い煙がMの周囲を包み、手足の感覚がない。ただひたすら全身の血潮がざわつき、波のように押し寄せる。
Mはただひたすら、あけたばかりの箱の中身を見ていた。しかし箱の中身は見えたはずなのに、一瞬先にはもう何を見たのか思い出せない。見えているのに見えていないそんな奇妙な世界の中にあるようだった。
この、煙は……人魂?かろうじてそんな思考回路だけが浮かんでは消え、いつしかMはすべての感覚を失っていた。
目を覚ますと、Mは自室のベッドの上にいた。
時刻は午後11時。暗くなった部屋の中で、昼間ほど暑くもないというのにMはびっしょりと汗をかいていた。まるで故意に霧吹きでもかけられたかのように大粒の汗が額を流れている。
そのとき、玄関のチャイムがなった。
インターフォンを確認すると、そこにはOがたっていた。
遅くなって悪かった。こんな深夜にカレーというのもなんだが、約束通り恐怖のカレーをもってきたんだ、今から一緒に食べよう。
Oは昼間とは打って変わってニコニコしながらそう言った。
…まったく、悪い夢を見たものだ。
昼間、日差しに当たり過ぎただろうか。
やはり、暑さというのは実に人を狂わせる…。
部屋の中には、スパイスの効いたカレーの香りがわずかに漂っていた。
(…という噂。)
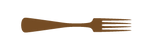
メニュー